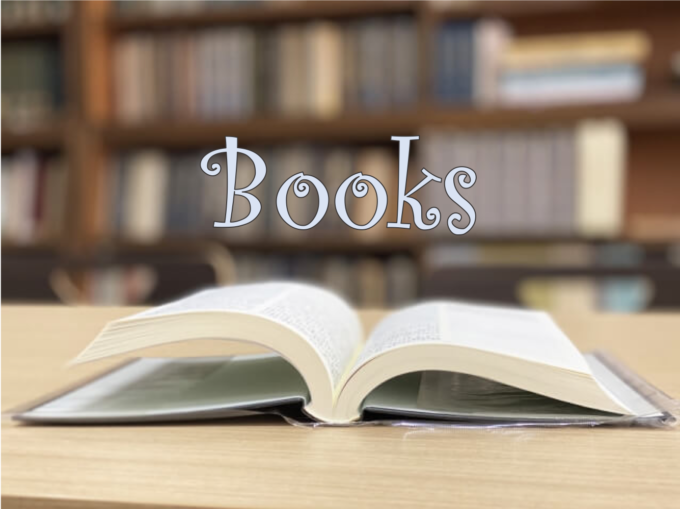こちらでは、朝井まかて氏の『残り者』(双葉文庫)をご紹介しています。

本から学んだことや感じたことを、徒然なるままに書いています。
物語の舞台は、江戸時代末期、幕末。
慶応4年(1868)4月10日・11日の、江戸城明け渡し前日と当日の江戸城・大奥です。
江戸城明け渡しとは、新政府軍(官軍)と旧幕府の間で行われた、江戸城の新政府軍への引き渡しと諸々の交渉のこと。
大きな争いや戦いで血を流すことなく城が明け渡されたので「無血開城」ともいわれます。
その時代の江戸城大奥の主人(あるじ)は、徳川家13代将軍・家定(いえさだ)の正室・天璋院(てんしょういん/鹿児島(薩摩)島津家の養女・篤姫)と、14代将軍・家茂(いえもち)の正室・静寛院宮(せいかんいんみや/孝明天皇の妹・和宮)です。
天璋院と、彼女に仕える総勢170人の奥女中が西の丸の大広間に勢揃いする場面から、物語ははじまります。
「ゆるゆると、急げ」
天璋院の命に従って、大奥から江戸の一橋邸へ大移動をする奥女中たち。
上を下への大騒ぎの中、物語の主人公・呉服之間の「りつ」は、大奥に後ろ髪を引かれるように仕事部屋であった呉服之間へ立ち寄り、これまでの大奥での奉公と暮らしを振り返ります。
そんな中、天璋院の愛猫・サト姫を探す御膳所の「お蛸」、天璋院が女将軍として大奥に戻ることを信じる御三之間の「ちか」、天璋院の新御殿にいた御中臈の「ふき」と静寛院宮方・呉服之間の「もみぢ」と出会います。
御目見得以上・以下と地位や立場・年齢も違う彼女たちは、通常の大奥では言葉を交わすこともなかったであろう「残り者」の5人です。
人生を捧げた大奥をそれぞれの理由で去りがたいの彼女たちは、胸のうちを語りはじめ、反発し共感しつつ最後の大奥の長い夜をともに過ごします。
奥女中の上下関係やしきたり、言葉使いや大奥での呼び名のことなど、謎に包まれた大奥の様子と奥女中たちの暮らしぶりが子細に表現されていて、とても興味深い作品です。
薩摩と天璋院の関係や、朝廷と静寛院宮の関係といった「奥」の女性に関することだけでなく、「表」の世界の政治や情勢が分かりやすく描かれているので、江戸城明け渡しに至る、幕末動乱期の時代背景を理解することができます。
開国を迫る外国船が現れるようになって参勤交代制が緩和されたことや、大奥法度のこと、大奥に奉公に入る際の血判誓紙の内容など興味深いものがありました。
3代将軍・家光公以降、およそ240年もの間、徳川家では天皇家や宮家・摂関家から正室を迎えてきたといいます。
「権力を掌中に収めた徳川家にとって、格下の大名家との婚姻はもはや何の旨みもなかろう」
「禁裏との連携を密にし、その威光を得ることで、諸大名への支配をより強固なものにすることができたのであろう」という記述には、なるほどと頷きました。
13代・家定公が、摂関家の養女になったとはいえ、一大名家である島津家の養女を正室に迎えたことは、幕末の幕府と大名家とのパワーバランスが乱れている証でしょう。
にもかかわらず、14代・家茂公は公武合体を目指して和宮が降嫁されたのですから、この御台所(みだいどころ/正室)の出自に目を向けるだけでも、幕末の混乱期を理解するきっかけになるだろうと感じました。
明け渡し前夜に大奥に残った5人の「残り者」。
強くて弱く、けれどもたくましい女性たちの姿に、新しいチャレンジや未来に向けて、前を見据える勇気をもらいました。

。
朝井まかて『残り者』
詳しくはこちら
。
。
では、また!